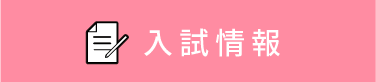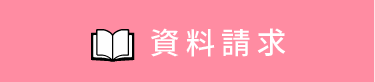授業で解説する社会的行動の中に「同調行動」というものがあります。これは「まわりの意見や行動に合わせて、自分も同じように行動してしまうこと」をいいます。同調行動自体は日常的によく観察される行動なのですが、この説明をすると授業後に「日本人は集団主義なので納得しましたが、個人主義的な外国でも同じことが起こるのでしょうか?」というコメントが毎年あります。私はいつもこのコメントを見て「なぜ?」と思うのですが、今回はそう思う理由や物事の捉え方、考え方について紹介します。

「常識」を疑おう
同調行動の研究はアッシュというアメリカの社会心理学者が始めたもので、授業でもアッシュの研究知見を紹介しています。なので、アメリカで同調行動が起こっており、その行動が研究されてきたことがわかります。
私がコメントに「なぜ?」と思うポイントは、主に二つあります。
ひとつは「なぜ『日本人=集団主義』と思っているのか?」という点、もうひとつは「なぜ『外国人=個人主義』と思っているのか?」という点です。
後者の理由は簡単です。上記の質問をする学生のイメージが「外国人=個人主義のアメリカ人」だからです。しかし実際には、アメリカでも地域によって個人主義的な傾向は異なりますし、アジアや中東なども外国なので、その中には集団主義的な国民性を持つ国が少なくありません。決して「外国人=個人主義」とひとくくりにはできないのです。
前者はどうでしょうか。おそらく、学生を含めた日本社会全体が「日本人=集団主義」という社会通念の影響を受けていて、疑うことなく常識だと思われているようです。しかし、その考えは本当に常識なのでしょうか?
コロナ禍に実施されたアメリカ・マサチューセッツ工科大などの研究チームの調査によると、アメリカやイギリスなど個人主義的な傾向が強いとされる国でマスク着用率は低く、日本は集団主義的な傾向はさほど高くないものの、マスク着用率は高かったという結果が出ています。実際にデータを見ても、日本は集団主義的な傾向は高くなく、集団主義的とは思われていないというのがわかります。
また、高校生を対象とした国際比較のデータでは、アメリカの高校生の方が日本の高校生よりも集団主義的に見えるものがあります。アメリカの学園ドラマを見てもらえるとわかり易いのですが、皆同じファッションスタイルで行動や思考も周りに合わせているようです。他方、日本の高校生は、皆と同じ思考や行動よりも「他人から見られる自分」を強く意識しています。この自分のことを気にしての行動は明らかに個人主義的です。つまり、日本の高校生は集団主義的に見える個人主義なのです。
「私が悪い」をやめよう
学生と接していると、過去に人間関係で悩みを抱えた経験のある人が多いことがわかりました。また、そうした経験があると話してくれる学生には、ある共通認識があることにも気づきました。それは「人間関係の問題の原因を『自分のせい』だ」と考えていることです。この自虐的思考が、不登校や引きこもり、体調不良の原因になっていることもあるように思います。
この自虐的思考は妥当な考え方なのでしょうか?
私はそうは思いません。たいていの人間関係的な問題は個人の責任に帰結させない方が良いと考えます。なぜなら人間関係的な問題は、本人が認識する以上に多くの要因が複雑に絡み合っているから。「誰が悪い」などと短絡的に考える問題ではないと思うのです。むしろ「誰が悪いか」ではなく「何が悪いか」を考えるべき問題で、そうすることで問題の本質が見えてくるのではないでしょうか。
多くの日本人が問題の責任を「何が」ではなく「誰が」に帰結させようとするのは、アメリカほど人材流動性が高くない日本の労働市場の中でアメリカ的な成果主義が進んだことで、原因や成果を個人に帰結させる自己責任的な考え方だけが残ってしまった結果と言えるでしょう。
世の中で起こる多くの問題はさまざまな原因が複合的に絡み合って起こるものであり、「自分が悪い」と単純に考えてしまうのは視野が狭いと言わざるを得ません。現在はSNSの発達により、意識して行動しないと情報環境すらエコーチェンバー化してしまう時代なのですから。
多様なものは多様に、複雑なものは複雑に考えよう
現在、世界ではパレスチナやウクライナだけではなく、アフリカやアジア、さらには北極圏にすら多くの問題が存在しています。それらのどれも、ひとつの原因や枠組みでは語れないほど、問題が複合的に絡み合っているのはご存じの通りです。
人は、物事を単純化して答えを一つにすることでスッキリした気持ちになります。逆に複合的なものを複合的に説明されてもスッキリできません。単純化して答えを一つにする方がわかりやすくて説得力も高く感じますが、実際にはそんな事象はほぼ存在しません。社会の出来事はすべて多様で複雑なのです。だからこそ複雑なものは複雑なまま捉え、多様なものは多様なまま捉えて考える意識を持ち続けたいものです。
学生の皆さんは物事を単純化せず、多様なものは多様に、複雑なものは複雑に考え、議論し、理解しようとする姿勢を持ち、あえて個人主義的思考を排除して、常に「誰が?」ではなく「何が?」を考えられる人をめざしてください。